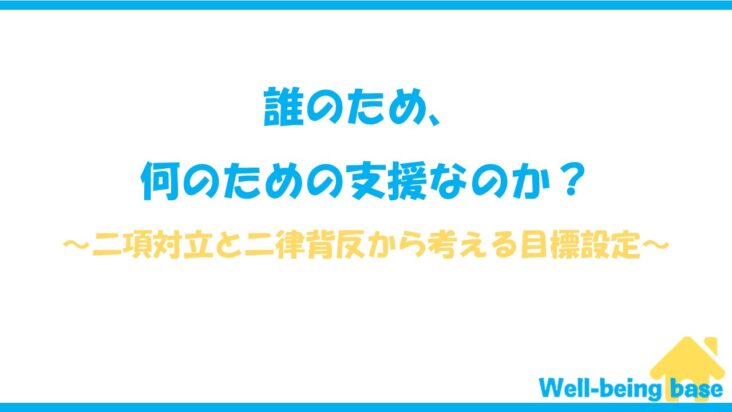 リハビリテーション
リハビリテーション誰のため、何のための支援なのか?~二項対立と二律背反から考える目標設定~
支援場面では、色々な立場のステークスホルダーが存在しそれぞれの立場でのニーズやデマンドがあり、聞いたままではすべての望みを叶えることはできません。表出されたニーズ、デマンドを深堀りすることで、みんなの本質的な望みを見つけ出し、共通点を探ることが必要です。
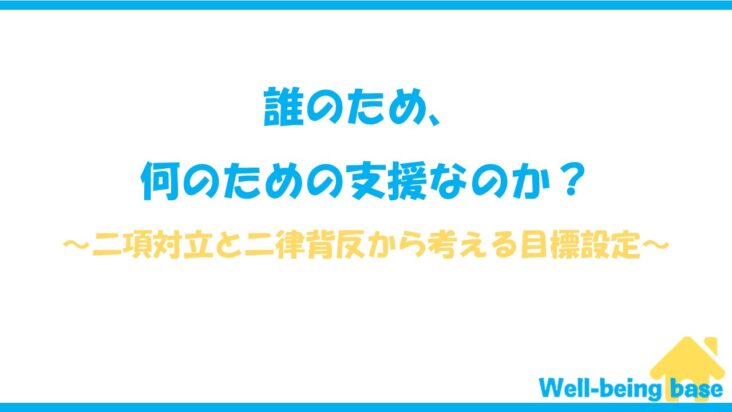 リハビリテーション
リハビリテーション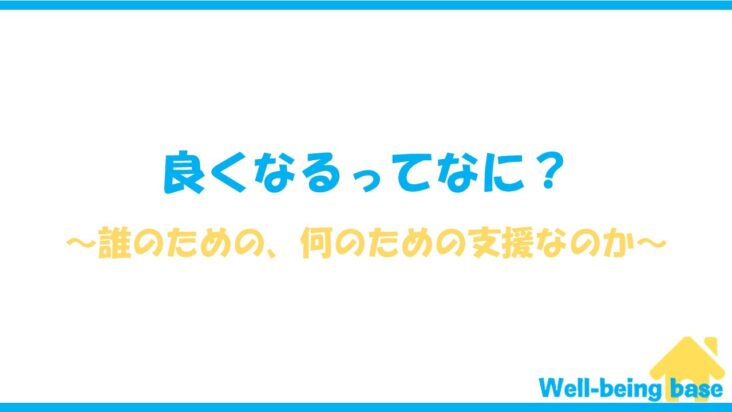 リハビリテーション
リハビリテーション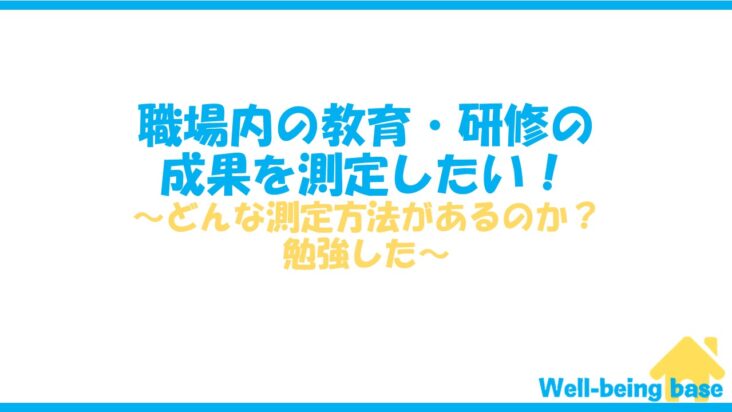 開業準備
開業準備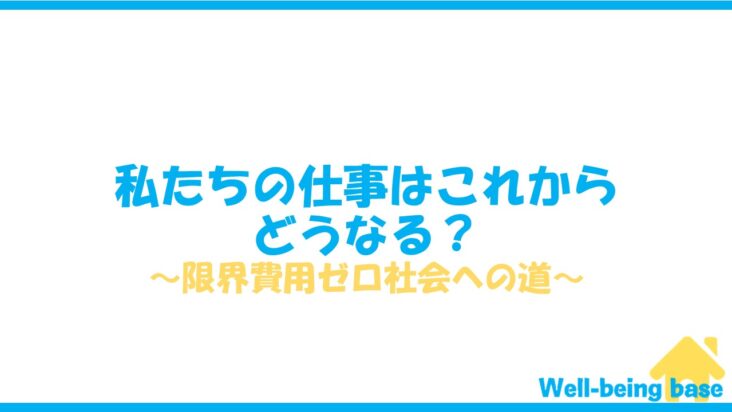 マーケティング
マーケティング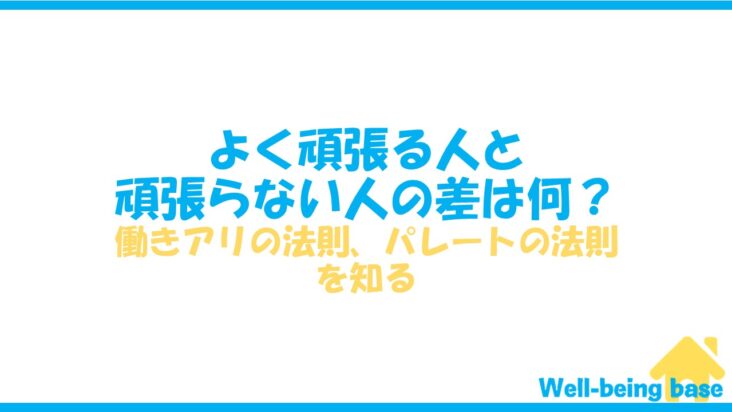 ビジネス心理学
ビジネス心理学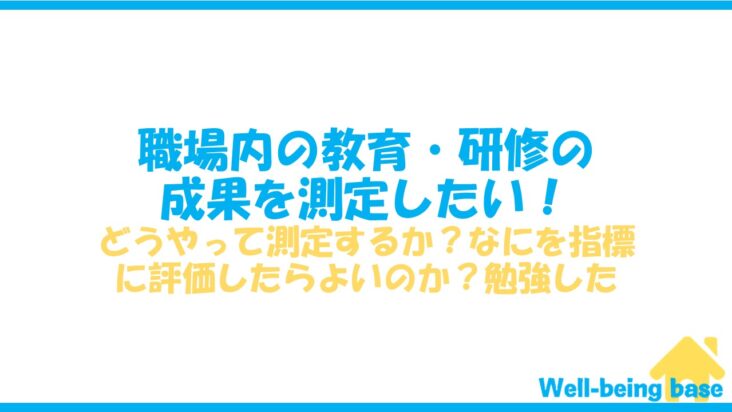 リハビリテーション
リハビリテーション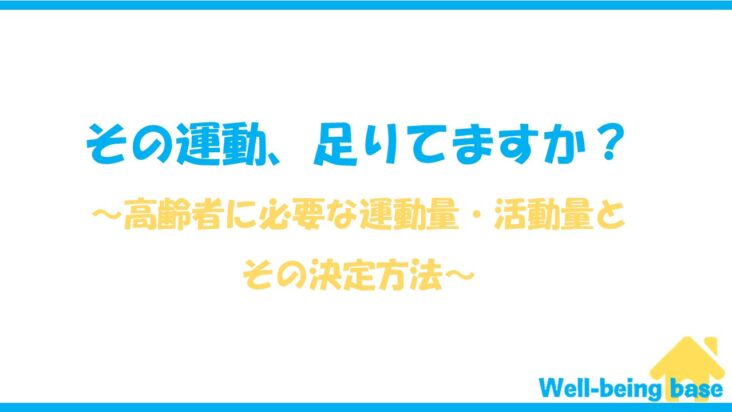 リハビリテーション
リハビリテーション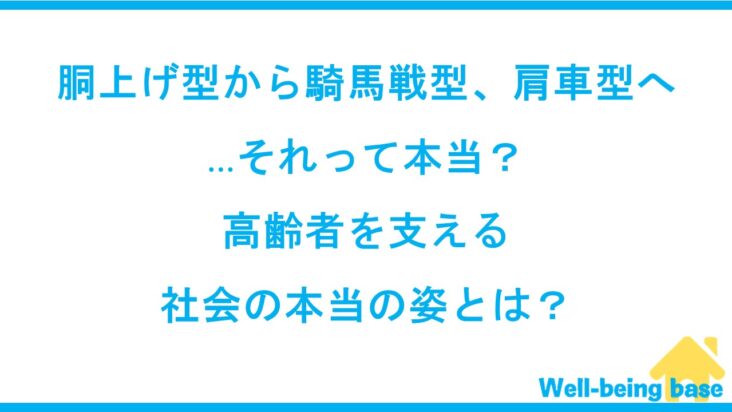 リハビリテーション
リハビリテーション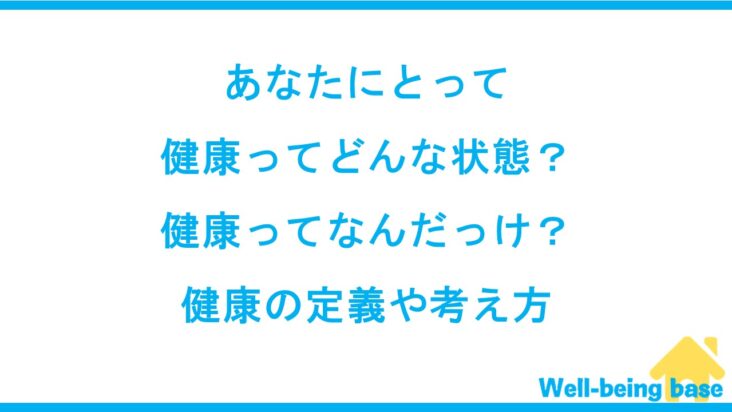 リハビリテーション
リハビリテーション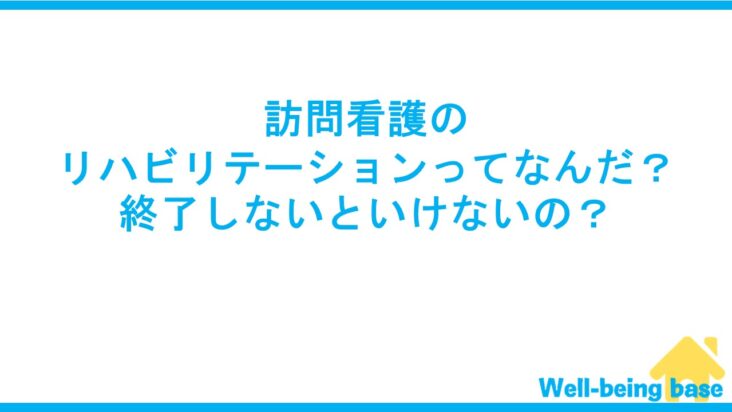 リハビリテーション
リハビリテーション